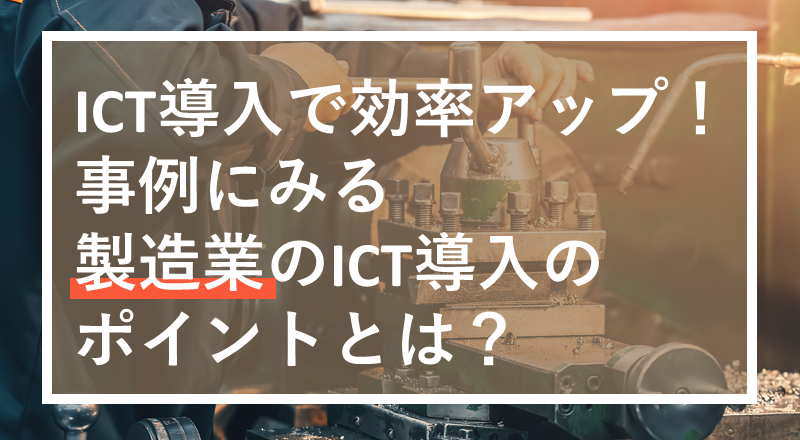
ICT導入で効率アップ|事例にみる製造業のICT導入のポイントとは?
2022年03月31日 06:00
この記事に書いてあること
ICT導入はイメージの具体化から
「ICT導入」と聞いただけで、気構えてしまう経営者は意外と多くいます。「パソコンを使うのは一部のメンバーだけ」、「うちは特殊な業務フローなので、システム導入は難しい」といった声も聞こえてきます。
一方で、業務フローを詳しく伺い、ICT導入について具体例を挙げながらディスカッションをすると、「なるほどね、それならできるかもしれない」、「全体での導入は難しいけれど、●●をICTで改善するだけでも大きな効果があるよ」という話になり、次にお会いしたときには導入に向けて前のめりになられている、といった経営者にお会いすることがよくあります。
どこから手を付ければ良いのかわかりにくいICT導入ですが、やはりイメージを具体化することが一番の近道です。このコラムでは、多くの会社で取り組まれたICT導入事例の一部をご紹介し、自社での導入を検討する際のヒントにしていただきたいと考えています。
営業マンの日報は「情報の宝庫」。クラウドによる「見える化」で新たな取り組み
#製造業(機械)の事例
営業部門と生産部門の日報をクラウド上で「見える化」することで、適切な在庫管理から受注拡大に繋げた山清電気の事例です。これまで営業部門の日報作成は徹底していなかったものの、業務に合わせた日報用のフォームを作成し、パソコンで入力できるようにしました。
この取り組みで重要な点は、「日報フォーム作成→クラウド化→在庫管理に反映」という流れができあがっていることです。日報フォーム作成により、日報作成の手間軽減、作成者による情報の偏りや漏れを防ぐことができます。加えて、クラウド化により他部署の方も情報へアクセスしやすくなり、日報データの活用に繋げやすいという下地ができました。そして、最大のポイントはデータを活用した改善活動を実際に進めていることです。従業員目線では、「管理されるツール」と思われがちな日報を、全社活動に生かされる「情報の宝庫」として認識されることは何よりもプラスです。
経営者の立場で考えた時も、何か変化あったとき、例えば例年に比べ受注が伸び悩んでいる場合、従業員へヒアリングを行うことはよくあります。しかし、事例のように日々の業務において、営業活動で収集した情報共有を進めておくと、その変化への気づきが早くなることが期待できます。また、従業員からの声は、ベテランや声が大きな人の発言が反映されがちですが、全社的な活動にすることで、新しい目線を持った若手従業員による気づきを取り込める可能性もあります。
FAX受信の自動PDF化&クラウド化により本格テレワーク可能体制へ
#製造業(その他)の事例
FAX注文の内容をクラウド化した信越工業の事例です。FAXで注文を受けるケースはまだまだ多く、大変参考になる事例です。
この取り組みにより、従来行っていたFAXを紙で出力、スキャンしてPDF化という作業がなくなりました。人手で作業をする場合は、「事務所スタッフがFAX受信にすぐ気づくこと」、「スキャンする作業に取り掛かれる余裕があること」というように、FAX受信から営業スタッフへの共有までにはいくつか課題があります。今回の自動化は、事務所スタッフの状況を問わず、外回りの営業スタッフがすぐに内容を確認できることはもちろん、受領したFAXそのものを見ながら、取引先へ電話連絡するといった次のアクションが取りやすいこともメリットです。
すでに業務運営に電子メールを活用している会社においては、取引先に対し、注文書を電子メールに添付する形で提供してもらえれば良いのではないか、という意見もあると思います。しかしながら、まだまだFAXで注文するスタイルを継続している会社は多く、「取引先の都合に合わせたICT導入」という分野があることに気づかされる事例です。
FAX注文書のクラウド化は、外回りする営業スタッフへの共有もありますが、製造現場との共有も同時に行うことができます。納期が厳しい案件であれば、材料や現場人員の手配を先行して行え、営業、製造のそれぞれの現場がタッグを組み、お客さまからの要望に応える体制作りが可能となります。
ICTを活用して地域を牽引 顧客本位の経営の確立、そのための業務の最適化
#製造業(その他)の事例
アルミ鋳造を行う田島軽金属での「新旧図面比較」へのICT導入の事例です。取引先からの部分的な設計図面変更を受け、新たな砂型のもととなる模型を作るときのお話です。
一般的に、新旧2枚の図面を比較し、変更点をくまなく探し出すという作業は、後工程を担当する技術スタッフが適任だと考えられます。それは、図面において手が加えられやすい箇所に対する知見があり、確認漏れを防ぐことができる可能性が高いからです。しかし、この考えは「社内にいるどの従業員が作業すると効率良いか」という議論であり、「目視でのチェックは正確性の確保も含め負担が大きい」という本質的な課題解決にはつながっていません。この人的作業の限界に目を向けてシステム導入を進めたのが、この事例のポイントです。「2枚の図面から、違いを探す」というような比較作業は、システムが得意とする分野であり、人が作業するよりも短時間で、かつ正確な結果を返してきます。
この事例では、通常の業務時間内に十分な作業時間を確保できず、時間外勤務でまかない、その時間は月間50時間もありました。システム導入により、当該業務の時間は大幅に削減され、かつ図面の比較確認に漏れがなくなりました。確認漏れ防止は、間違った模型や砂型作成による無駄という直接的なコストのほか、時間という間接的なコストも抑えます。もちろん最終的には、取引先への納期短縮や信頼向上というものにつながります。
ICT導入では必ず導入コストが議論されますが、金額の多寡のみが注目されることも少なくありません。経営の観点においては、金額の多寡のみならず、導入によって得られる直接的、間接的メリットを見ながら意思決定されることをお勧めいたします。
なお、類似する事例として、シミュレーションシステムを活用する「製造業でも本番前のシミュレーションで大きな効果 淡路島を拠点に事業拡大する岡田シェル製作所(兵庫県)」もご覧ください。
世界を目指す川原食品にとって、食品安全マネジメントHACCP対応は必然の道
#製造業(食料品)の事例
柚子こしょうをはじめとする食品製造の川原食品におけるHACCP(ハサップ)対応の事例です。HACCPはHazard Analysis Critical Control Pointの頭文字を取ったもので、食品の安全を脅かす危険要因が混入するリスクを見つけ出す管理、記録する衛生管理手法です。フローダイアグラムやハザード分析表、管理表などの文書を作成する必要があり、HACCP文書作成システムを活用し、対応しました。
このシステム導入のポイントは、「素早く簡単に、誰でも更新できること」にあります。わざわざシステムを導入しなくても、インターネット上で見つけられる文書フォーマットを、そのまま利用、更新すれば良いのではないか、という意見もあると思います。ただ、HACCPの文書管理において大切なことは、最新であり、かつ正確であることです。特定の人しか作業できない、作業には時間がかかるので残業対応になる、ということであれば、更新作業は滞ってしまいます。
また、手作業による更新は、作業漏れが発生することがあります。せっかく更新した文書が正しい内容でなければ、意味はありません。更新漏れや文書間の整合性をチェックしてくれるのは、システムならではの強みと言えます。
HACCPはもちろん規格全般に言えますが、マニュアル類を整備し、認証、認定を受けることがゴールではありません。取り組みの「見える化」を通じ、一定の品質を確保し続けることに意味があります。そのためには、適切なタイミングでの情報更新が必須となりますが、システムの活用により、時間とリスクを最小化することができます。
「高技術のものづくり企業」の業務を支えるにはパートナー企業の存在が不可欠だった 寺方工作所(鳥取県)
#製造業(その他)の事例
社内スタッフが自社のホームページに「採用特設サイト」を作成、運営している寺方工作所の事例です。会社概要や商品・サービスをホームページで伝える会社は一定数ありますが、「採用特設サイト」を自社で制作している会社は中小製造業ではまだまだ少なく、注目の事例です。
「採用特設サイト」は、現状、知人の紹介などで効率よく人材が確保されているものの、「新しい人材を広く集めたい」という思いからスタ ートされました。このホームページのポイントは、「パッケージサービスの活用により負荷を抑え、社内スタッフがページを作成、運営をしている」という点です。一般的に外部の制作会社にホームページを構築してもらうと、更新のたびに費用がかかり、タイムリーな情報提供ができないという課題があります。しかし、パッケージサービスの導入により、専門人材を抱えることなく最小限のコストで、面倒なスマートフォン対応サイトも含め自社で作成されています。そのうえ、制作データを活用し、会社紹介のパンプレットもほぼ自動で作られています。
大学生・大学院生を対象とした「就職プロセス調査(*)」によると、「応募の決め手となった情報源」では、「個別企業の説明会・セミナー」に次いで、「企業からの情報(資料・Webサイト等)」とあります。また、「就職先を確定する際に決め手となった項目」の第1位が「自らの成長が期待できる」ともあります。
こうした学生の思いにあった情報提供は、潤沢な採用予算を持つ大企業だけのもの、という訳ではなくなってきました。ぜひ、自社の魅力を自分たちの言葉で語りかけ、優秀な学生の採用へと繋げてください。
*出典:リクルート 就職みらい研究所調べ
できることからコツコツと 小さな工場が始めたICT経営
#製造業(その他)の事例
最後にご紹介したいのは、コツコツとICT化を進められた中川商工の事例です。パソコンが1台もないところから、どのように取り組まれたかご覧いただきたい事例です。
この田村社長の取り組みで注目すべき点は、会社の規模を踏まえ、社内ICT化の助言を外部専門家に求めたことです。社長お一人で抱え込まれずに、外部専門家との相談を効果的に活用し、「納期の見える化」を実現されました。
ICT導入は、経営者が考える「会社のありたい姿」と現状とのギャップを埋めるための1つの手段と言えます。しかし、通常業務もある中で多くの時間を割くことは現実的には難しいと思われますので、経験豊富な外部専門家を壁打ち相手にし、ディスカッションすることが重要です。その際、どのようなツールがあるのかという情報も大事ですが、「どのように導入し、社内に定着させ、狙っている効果を獲得するか」という議論も丁寧に行っていただくことが大切です。
ICT導入に向けて必要な観点はQCD
ご紹介した事例のうち、ご自身の会社に当てはめて考えていただけそうなものはありましたか。
事例では、様々な効果が示されていましたが、
・正確性が増すことによる品質の向上
・業務効率の向上によるコスト削減
・納期短縮といった顧客サービスの向上
のように製造業において耳にするQCD[キューシーディ(Quality、Cost、Delivery:品質、コスト、納期)]と同じ観点でまずは考えていただくと、取り組む目的が整理しやすくなります。
紹介した事例を振り返ってみると、「HACCP文書作成システムの導入」は品質の向上、「システムでの新旧図面比較」はコスト削減、「受信したFAX情報のクラウド化」は納期短縮、と整理することができます。
はっきりとした目的を持たずに取り組むと、ICT導入がゴールになってしまいます。「ICT導入によって何を実現するか」、「QCDに効くのか」と十分な整理ができていれば、導入後の改善活動も明確になってきます。
本ホームページの上部には、「事例集」というタブがあり、コラムでは扱えなかった事例も多く掲載されています。「この事例は、QCDの何に効果があったのか?」という観点で、ぜひご覧いただき、自社でのICT導入に向けてイメージを膨らませてください。

記事執筆
伊藤 展慶(いとう のぶよし)
中小企業診断士、経営管理修士(MBA)、技術経営修士。経営コンサルティング事務所 NICS(ニックス)代表。製造、小売、IT、金融での職務経験から守備領域が広い。製造業を中心に、小売業、情報サービス業の経営者に寄り添った企業支援に取り組む。ICT導入や販路開拓の支援多数。 日本マーケティング学会会員。
記事タイトルとURLをコピーしました!









