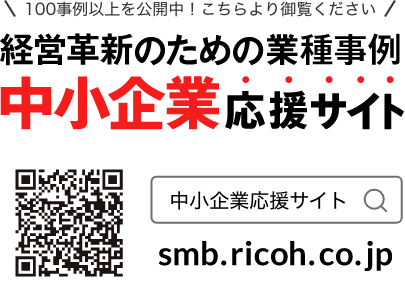建設業(土木)
建設業(建築)
建設業(設備)
製造業(食料品)
製造業(化学)
製造業(医薬品)
製造業(機械)
製造業(印刷)
製造業(その他)
小売業
サービス業
福祉介護
医療
その他

コラム
2022.12.08 06:00
リスクアセスメントとは?基本的な進め方やメリットを解説!
- #建設業(土木)
- #建設業(建築)
- #建設業(設備)
- #製造業(食料品)
- #製造業(化学)
- #製造業(医薬品)
- #製造業(機械)
- #製造業(印刷)
- #製造業(その他)
- #小売業
- #サービス業
- #福祉介護
- #医療
- #その他
- #顧客満足・社員満足度向上
- #聞くに聞けない経営用語

この記事に書いてあること



聞くに聞けない経営用語集vol.1
ビジネスよく耳にする経営用語の意味、ちゃんと理解して使っていますか?用語の使い方や、似ている用語の違い、中小企業経営に役立つ情報もあわせて解説した、経営用語集を無料配布中!
リスクアセスメントとは?1行で解説すると
リスクアセスメントとは、職場における労災リスクを調査し、それを低減・解消する対策を行うこと。
リスクアセスメントとは
リスクアセスメントとは、職場にある危険性や有害性を特定し、そのリスクの除去・低減措置を行う一連の手順です。作業場に潜む要因が起こす労働災害や健康障害の重篤度と、発生の可能性に応じてリスクを見積もり、その水準に従って具体策の優先順位を決定。リスクへの対処を検討、実施します。
リスクアセスメントという言葉の使い方
リスクアセスメントという言葉は、職場の安全性や、労災防止策について議論する際に用いられます。「リスクアセスメントを実行する」「リスクアセスメントに基づいた対策」「リスクアセスメントが重要である」といった使い方が一般的です。
ほかにもこの言葉の意味はご存知ですか?
リスクアセスメントという言葉以外にも、アセスメント、トレーサビリティなど、聞いたことはあるけれども使いこなせていない用語はありませんか? 中小企業応援サイト独自の資料「聞くに聞けない経営用語集」では、10のよく聞くビジネス用語を解説しています。経営に役立つ用語をマスターしたい方は、ぜひご覧ください。
中小企業こそリスクアセスメントが必要な理由
安全な職場を実現するために必要な、リスクアセスメント。災害や社員の健康障害を防ぐことは、中小企業にとって特に重要な取り組みです。その主な理由を、4つのステークホルダーの観点から解説します。
ステークホルダー別に考えた場合① 従業員
企業経営にとって大切な従業員を守るために、リスクアセスメントは欠かせません。事業所内の事故や、仕事中の負荷による心身の不調から人材を守るために、リスクを取り除く措置を行う必要があります。
また、安全な職場環境を作ることは、従業員満足度を高め、働く人のモチベーションアップにもつながります。人材難の時代に従業員の離職を防ぎ、長く安心して働ける職場を実現するためにも、リスクアセスメントを推進しましょう。
ステークホルダー別に考えた場合② 下請け先
下請け先に業務を委託している事業者は、請負企業の労災を防ぐためにも、リスクアセスメントの結果を下請け先に共有する必要があります。委託作業の安全衛生上注意すべき点や、製造で扱う原材料に関する危険性や有害性、防護方法や応急処置などについて情報を提供し、下請け先の事業所や労働者の安全を確保しましょう。
また、またリスクアセスメントは、下請け先を含む取引先からの信頼獲得にもつながります。社外との継続的な取引のためにも、労災や、従業員への負荷を減らす取り組みを進めましょう。
ステークホルダー別に考えた場合③ 購買者
一般消費者や顧客など、購買者からの信頼を得るためにもリスクアセスメントは重要です。事業所内での労災や事故が、企業や商品、サービスに対する信頼感や好感度に影響するからです。安全への対策が不十分な企業という印象によって企業価値が下がり、売上や株価の低下につながるため注意が必要です。
また、労災による休職、また労働環境を理由にした従業員の退職によって人材が不足すると、製品やサービスの質が低下します。購買者に安定して高品質な商品を届けるためにも、従業員の安全を守ることは不可欠です。
ステークホルダー別に考えた場合④ 採用に向けて
従業員の満足度アップや離職対策だけでなく、新卒採用や中途採用などの人材獲得の観点からも、職場の安全性を高める取り組みは効果的です。
リスクアセスメントが徹底され、労災リスクが低く安心して働ける職場は、求職者にとっても魅力的です。応募者数を上げて優秀な人材を安定的に確保するためにも、リスクアセスメントを徹底しましょう。
リスクアセスメントを実施する際に必要な体制とは?
リスクアセスメント導入を成功させるために、社内のリスクアセスメント実施体制を十分に整えましょう。まずは、経営トップ、または事業所長や工場長が、職場の安全衛生管理活動のひとつとしてリスクアセスメントを実施することを表明します。その上で、安全管理者や製造部門の責任者など、現場をよく知る従業員を集めた推進メンバーを決めましょう。
正確にリスクを見積もり効果的な対策を決めるためには、仕事中に感じた危険性などの一般社員の声が必要です。そのため、リスクアセスメントは、すべての従業員にヒアリングを行うなどして、全社の協力のもとで行うのが理想的です。
リスクアセスメントの基本的な進め方
では、リスクアセスメントは具体的にどのように進めれば良いのでしょうか。
労働安全衛生法では、リスクアセスメント実施義務の条件となる化学物質や実施すべきタイミングを定めています。また、下記のステップに従って事業所のリスクアセスメントを進めるよう、規定しています。
①危険性または有害性の特定
作業手順書、機械の取り扱い説明書、自社や他社の労働災害事例、また現場の従業員が感じた職場の危険性に関するメモなど、資料を集めます。そして、職場のすべての工程ごとに、全作業中の危険性や有害性を洗い出し、発生可能性のある災害を特定しましょう。
災害に至るまでのプロセスを正確に予測するため、「~なので、~して」「~なので」+「~になる」「~する」という形で、原因と結果を具体的に記載するのがポイントです。
②リスクの見積もり
次に、①で特定した要因による労災や健康障害の重篤性と、その災害が発生する可能性や頻度を組み合わせて、リスクを見積もります。重篤性と可能性、頻度を足した「評価点数(リスクポイント)」を算出し、危険性に対処する優先度を決定します。
リスクの見積もりは、複数の視点から適切な判断を行うため複数人で実施すること、上位職だけでなく、作業内容をよく知る人の意見を反映すること、根拠のある数字を見積もることが大切です。また重篤度は、過去に発生した災害事例に基づくのではなく、最悪のケースを想定して見積もりましょう。
③リスク低減措置の内容検討
次に、リスクを低減するための措置の内容を検討します。法令に定められた事項は必ず措置を行った上で、リスクポイントが高いものから優先的に進めます。それぞれのリスクに対して行うべき安全衛生対策内容の優先順位は、以下のとおりです。
①設計や計画の段階における危険性・有害性の除去または低減
リスクの高い作業の廃止・変更、危険性や有害性の低い材料への代替、より安全な施行方法への変更など
②工学的対策
ガード、インターロック、安全装置導入などの物的な対策
③管理的対策
マニュアルの整備、立ち入り禁止措置、教育訓練などの人的対策
④個人用保護具の使用
上記の措置を講じても除去・低減しきれなかったリスクに対して、保護帽、安全靴、保護衣などの保護具を使用する対策
④リスク低減措置の実施
対処の優先順位と検討したリスク低減措置内容をもとに、リスクアセスメント担当者が具体的な取り組みを実施します。
業務の計画段階から危険な作業や原料を取り除くことを最優先に考えて、それが難しい場合は、物的、管理的な対策を行います。個人用保護具は、それでも防げない場合の最終手段として実施しましょう。
⑤リスクアセスメント結果の労働者への周知
リスクアセスメントを実施した後は、その結果を従業員に周知します。リスクアセスメントの対象物の名称、対象業務、リスクアセスメントによって特定した危険性やリスクなどの結果、実施するリスク低減措置について、掲示や書面、常時確認可能なパソコン端末のいずれかの方法で伝えましょう。
また、実施の結果をふまえて、次年度以降のリスクアセスメントを含めた安全衛生目標と安全衛生計画を策定します。リスクアセスメントを継続して行い、職場の安全衛生水準を向上させていくことが大切です。
業種別に確認しておきたいリスクアセスメント
労働安全衛生法では、製造業等ではリスクアセスメントを行うよう努力しなければならないと定めています。また業種に関わらず、法律で定められた一定の危険有害性がある化学物質の製造・取り扱いを行う事業所で、リスクアセスメントは義務化されています。危険性のある化学物質は、製造業、建設業だけでなく、清掃業、小売業、飲食業、医療、福祉業など、さまざまな業種で使われているので、注意が必要です。
では、リスクアセスメントは、業界の特性に応じて意識すべきことはあるのでしょうか? 業種別のリスクアセスメントのポイントを解説します。
製造業
大型機械の使用や加工、運搬作業など、工場での作業員の負荷が多い製造業は、労災が起こりやすい業界のひとつです。人材不足も進む中で、ひとりひとりの作業量の増加に伴う健康被害も増えています。
製造業では、転落や転倒、交通事故、はさまれによる事故などが多く、死亡事故も発生しています。重大な事故を招く作業自体をなくす、または別の作業に置き換えることを最優先に行い、それが難しい場合は、作業環境の改善や、安全カバーや非常停止センサー、防火装置の取り付けといったリスク低減措置を採用しましょう。従業員見守りシステムなど、ITを活用した施策も安全性向上に有効です。
建設業
建設業での労災は、死亡災害が全産業の発生数のうち3分の1を占めるなど、多く発生しています。その主な原因は、墜落や転落、転倒や激突など。重層的な請負構造がある建設業界には、競争激化や経営状況の悪化から、安全対策が徹底されにくいという問題もあります。このような業界の特性から、労働安全衛生法では、元方事業者が統括管理を行うこと、関係請負人を含めた安全衛生責任体制の確立を基本に、関係事業者が必要な安全衛生対策を講じることが規定されています。
そのため、建設業では、同じ作業場で複数の事業者が作業することがある、条件が異なる案件ごとに作業を覚える必要があることなどを考慮してリスクアセスメントを進める必要があります。各事業者は、作業の計画段階から時間をかけて、設備や配置上の問題を解決しておくことが重要です。
福祉介護業
福祉介護業を含む第三次産業でも、労災件数は年々増加しています。社会福祉施設での労災による死傷者数も増えており、今後、高齢化で介護福祉業で働く人のニーズも高まる中、さらに労災が増えることが懸念されています。
利用者に安全な生活環境を提供するためには、まずは職員が安全かつ健康に働ける環境を整えることが必須です。食事や入浴などの利用者の生活支援は体力も気配りも求められる上に、無理な姿勢での作業に伴う腰痛や、介助中の転倒、車椅子による事故、また利用者からの暴力など、福祉介護業特有のリスクもあります。職員の心身の健康を阻害する要因を正しく見積もり、対処することが重要です。
医療業
医療業界でも、安全な労働環境を実現するリスクアセスメントは重要です。看護職など、医療現場で働く人の就業環境には、身体に悪影響を与える要因のほか、化学物質や病原体による健康被害など、医療業界特有のリスクもあります。職員は、患者の体位調整や抱き上げ、電子機器の使用による筋骨格系障害のほか、消毒剤や抗がん剤などの薬剤、そして人体に有害な化学物質、また飛沫や接触、汚染物などを介したウイルスや細菌の感染リスクにも晒されています。
夜勤交代制勤務や長時間労働に伴う生活リズムの乱れや不眠、疲労による心身の活動性の低下など、不規則な働き方に起因する健康被害も起きています。有害な要因への対処やメンタルヘルスケアなど、幅広い対策が求められるのが、医療業界のリスクアセスメントの特徴です。
保育・学校
保育所や幼稚園、小学校など、子どもをケアする施設にも、職員の健康被害を招く要因が多く存在します。子どもが安心して過ごせる環境を整えるためにも、まずは労災を防ぐことが大切です。
ピアノなどの重量物の倒壊対策、ぶつかってけがをする恐れがある角を保護する、転倒の原因となる段差を解消するなど、ケガ防止策を行うほか、園児の午睡中の暗い環境や高温多湿での作業など、体の不調を招く要因を排除することも大切です。また、調理室の危険性に対処するリスクアセスメントも欠かせません。やけど、熱中症、腰痛など、調理中の事故を招く要因を特定し、作業場の改善を行いましょう。
リスクアセスメント導入のメリット
リスクアセスメントの最大のメリットは、職場の労災を防ぎ、働く人の安全を確保できることです。厚生労働省の調査によると、リスクアセスメントとそれに基づくリスク低減措置を行っている事業所は、行っていない事業所と比較して災害の発生率が大幅に下がっています。
また、リスクアセスメントを行うことで、従業員の間で、職場のリスクに対する高い意識を共有できます。また、リスクアセスメントの合理的なステップを通して導かれた必要な安全対策やルールを、従業員が納得して徹底できるようになります。安心して働ける職場環境が実現することで、従業員満足度が上がり仕事へのモチベーションを高められるのも、リスクアセスメントのメリットです。
聞くに聞けない経営用語集
ステークホルダーからの信頼や、人材面でも意義のあるリスクアセスメント。用語の意味や重要性を理解できたら、次は、自社でのリスクアセスメントの取り組みを進めてみてはいかがでしょうか?
中小企業応援サイトでは、リスクアセスメントのほか、ガバナンス、アライアンス、コンプライアンスなど、ビジネスでの会話に役立つ用語を解説する「聞くに聞けない経営用語集」のダウンロードを実施中です。経営者としての基礎知識を学ぶ資料としてご活用ください。


聞くに聞けない経営用語集vol.1
ビジネスよく耳にする経営用語の意味、ちゃんと理解して使っていますか?用語の使い方や、似ている用語の違い、中小企業経営に役立つ情報もあわせて解説した、経営用語集を無料配布中!