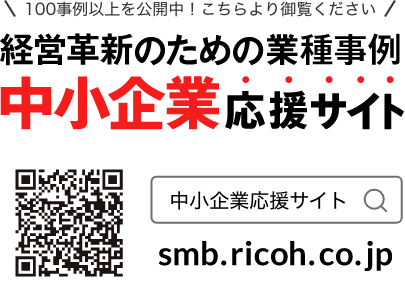コラム
2023.09.22 06:00
【2023年度版】人手不足の解消や職場環境改善に!活用できる助成金を紹介
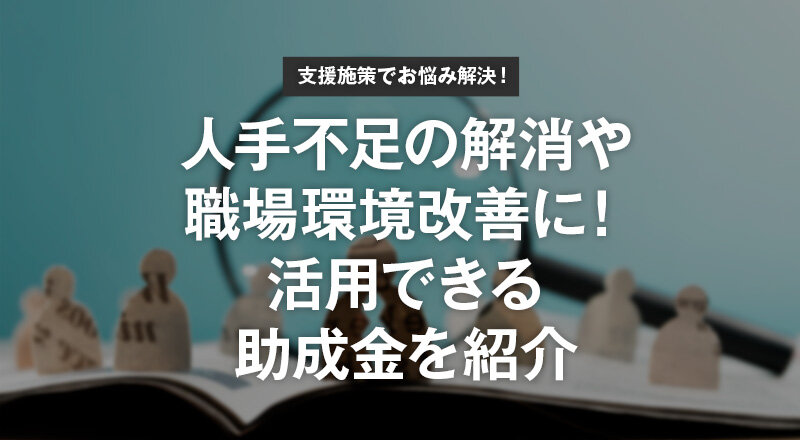
この記事に書いてあること
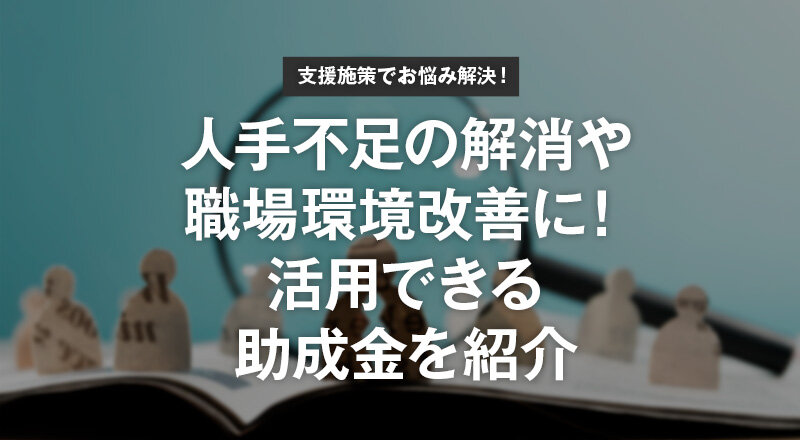

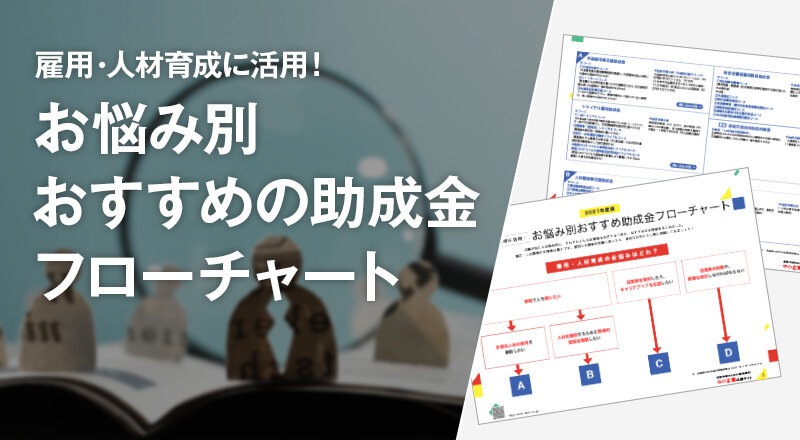
【2023年度版】雇用・人材育成に活用!お悩み別おすすめ助成金フローチャート
代表的な支援策の中から、企業のお悩みに合わせておすすめのものを紹介するフローチャートをご用意しました。ぜひ自社に関係ある支援策を知り、雇用・人材育成活動にお役立てください。
※本記事の内容は、記事作成日(2023年7月)時点の情報に基づいています。最新の情報は各施策の公式サイトなどをご参照ください。
人材面で悩む中小企業をサポートする助成金などの支援策
少子高齢化による労働人口の減少が進む中、中小企業が優秀な人材を確保することは、年々難しくなってきています。
その一方で、働き方改革によるダイバーシティの推進、アフターコロナの就業意識の変化などにより、従来とは異なる採用や職場環境の整備が求められています。
国や自治体でも、中小企業の雇用や人材の定着、職場環境の整備のため、さまざまな支援策を用意しています。今回はそれらの中から主なものをご紹介します。
雇用・労働関係の施策を管轄する国の機関は、厚生労働省(厚労省)です。そのため、人材関連支援策の主なものは、厚労省の助成金になります。また、地方自治体が独自の支援策をおこなっている場合もあります。
助成金と補助金との違い
ところで「助成金」と、IT導入補助金のような「補助金」とはどう違うのでしょうか?
まず、「助成金」は厚労省関係の施策につけられる呼称であり、「補助金」は経済産業省ならびに中小企業庁関連の施策で用いられる呼称だという点です。「助成」と「補助」の言葉自体の意味に違いはありませんが、慣習により使いわけられています。
もうひとつ、採択に関する違いがあります。
助成金は、助成要件に合致する企業が申請すれば、原則的にすべて助成を受けることができます(要件に合致しているかどうかの審査はあります)。それに対して、補助金は採択に関する審査があり、外形的な要件に合致している企業が申請してもすべてが採択されるわけではありません。
また助成金は、原則的に通年いつでも応募できますが、補助金は比較的短い「公募期間」が定められており、そのスケジュールに従って応募しなければなりません。
なお、上記は国の施策に関するものであり、地方自治体の支援施策にも「助成金」と「補助金」があります。
本記事で紹介する施策
厚労省管轄の助成金は、その対象となる人材や企業の状況などにより、非常に多くの種類にわかれています。ここではその中から選んだ、以下の施策を紹介します。
人材を採用することでもらえる助成金
人材確保のための職場環境整備に関する助成金
人材育成・キャリア開発に関する支援策
雇用維持、雇用調整に関する支援策
地方自治体独自制度
人材を採用することでもらえる助成金
人材採用でもらえる主な助成金として、採用対象者ごとに異なる下記の3種類があります。
- ・
中途採用等支援助成金
- ・
特定求職者雇用開発助成金
- ・
トライアル雇用助成金
中途採用等支援助成金
中途採用等支援助成金は、終身雇用制度の崩壊とともに増加する転職者の中途採用を促すための助成金で、下記の2コースがあります。
中途採用等支援助成金
中途採用拡大コース
中途採用者の雇用管理制度を整備し、中途採用の拡大を図った場合に助成されるもの
UIJターンコース
東京圏からの移住者を雇い入れた事業主に対し、その採用活動に要した経費の一部が助成されるもの
ここでは、一般的な「中途採用拡大コース」について解説します。
「中途採用拡大コース」の支給要件
中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)は、中途採用者の雇用管理制度を整備し、中途採用の拡大を図った場合に「中途採用拡大助成」が受けられます。
主な支給要件は下記の通りです。
▼中途採用拡大助成の主な支給要件
- ・
中途採用者の雇用管理制度(募集・採用以外、新卒者に適用されるものと同じ制度)を整備すること。
- ・
中途採用計画を作成し、管轄の労働局に届け出ること。
- ・
中途採用率を20ポイント以上向上させること。45歳以上の人の中途採用率が10ポイント以上向上するなどにした場合は増額。
「中途採用拡大コース」の支給額
▼中途採用拡大助成の支給額
中途採用率の拡大が20ポイント以上:50万円
45歳以上の人の中途採用率も10ポイント以上拡大:100万円
特定求職者雇用開発助成金
特定求職者雇用開発助成金とは、高年齢者、障害者、母子家庭の母などの就職困難者を、ハローワーク等の紹介により、雇用保険の一般被保険者として雇用する際に受けられる助成金です。これは、下記の5つのコースにわかれています。
特定求職者雇用開発助成金
特定就職困難者コース
対象:高年齢者・障害者・母子家庭の母等
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
対象:発達障害者または難治性疾患患者
就職氷河期世代安定雇用実現コース
対象:正規雇用の機会を逃したこと等により、十分なキャリア形成がなされず、正規雇用に就くことが困難な者
生活保護受給者等雇用開発コース
対象:自治体からハローワークに就労支援の要請があった生活保護受給者等
成長分野人材確保・育成コース
対象:上記4コースの対象者のいずれか(デジタル、グリーン関連業務など成長分野の業務で雇用する場合)
ここでは、「特定就職困難者コース」について紹介します。「生涯現役コース」の廃止に伴い、65歳以上の人も対象となりました。
「特定就職困難者コース」の支給要件
▼助成対象となる特定就職困難者
- ・
60歳以上の高年齢者
- ・
母子家庭の母等
- ・
身体・知的障害者
- ・
重度障害者等(重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者)など
▼支給要件
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の支給要件は次の2つです。
- ・
ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
- ・
雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であること
なお、「継続して雇用」とは、65歳以上まで継続雇用することと雇用期間が2年以上あることです。
「特定就職困難者コース」の支給額
支給額は、労働者1人当たりの金額で、対象となる労働者の類型と、企業規模の組み合わせによって決まります。
(例)
- ・
短時間労働者(※)以外で、高年齢者(60歳以上)、母子家庭の母等を雇用する場合:1年間で60万円(中小企業の場合)
- ・
短時間労働者で、高年齢者(60歳以上)、母子家庭の母等を雇用する場合:1年間で40万円(中小企業の場合)
※1週間の所定労働時間20時間以上30時間未満
トライアル雇用助成金
トライアル雇用助成金は、職業経験・技能・知識の不足などの理由で就職が困難な求職者を、原則として3ヶ月間試行雇用した事業主に対し支給されます。
トライアル期間に適性や能力を見極め、常用雇用への移行のきっかけとすることを目的とし、下記の3コースがあります。
トライアル雇用助成金
対象:55歳未満で、安定所等で個別支援を受けている者、離職期間1年超の者、出産・育児等で離職し1年超離職している者等
障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース
対象:就職困難な障害者
若年・女性建設労働者トライアルコース
対象:若年者(35歳未満)または女性(建設業の中小事業主が建設技能労働者等として試行雇用する場合)
「一般トライアルコース」の支給要件と支給額
ここでは、「一般トライアルコース」について紹介します。主な支給要件は下記の通りです。
(例)
- ・ハローワーク、紹介事業者等の紹介により雇い入れること
- ・原則3ヶ月のトライアル雇用をすること
- ・1週間の所定労働時間が原則として通常の労働者と同程度(30時間)であること
など
支給額は、原則として、支給対象者1人につき月額4万円(対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合5万円)です。なお、就労日数などに応じた例外があります。また、支給対象期間は最長3ヶ月です。
人材確保のための職場環境整備に関する助成金
職場環境や雇用管理制度を整備し、労働者が働きやすい環境をつくることにより人材の定着を目指すタイプの助成金です。主なものは下記の通りです。
- ・働き方改革推進支援助成金
- ・業務改善助成金
- ・人材確保等支援助成金
- ・両立支援等助成金
働き方改革推進支援助成金
働き方改革推進支援助成金は、生産性を高めて労働時間の縮減などに取り組む企業を支援する助成金です。下記の5つのコースがあり、「適用猶予業種等対応コース」は、2024年4月に時間外労働の上限規制が適用される建設業、運送業を支援するため新設されました。
働き方改革推進支援助成金
労働時間短縮・年休促進支援コース
時間外労働の削減や有給休暇の取得促進に向けた取り組み
勤務間インターバル導入コース
勤務間インターバル制度の導入と拡充
労働時間適正管理推進コース
労務管理書類の保存期間延長や労働時間の適正な把握に関する取り組み
団体推進コース
事業主団体などによる傘下企業の時間外労働削減などに対する取り組み
適用猶予業種等対応コース
建設業、運送業、病院等、砂糖製造業の中小企業
「労働時間短縮・年休促進支援コース」の支給要件と支給額
ここでは、「労働時間短縮・年休促進支援コース」について紹介します。主な支給要件は下記の通りです。
(例)
- ・「就業規則・労使協定等の作成・変更」など所定の取り組みを1つ以上実施
- ・時間外労働と休日労働の合計時間を80時間以内に抑えるなどの成果目標の達成
達成した成果目標によって次の金額を上限に支給金額が決定します。また、賃金引き上げによる加算もあります。
- ・時間外労働時間などが60時間以内:200万円(※)
- ・時間外労働時間などが80時間以内:100万円(※)
- ・有給休暇の計画的付与制度を新規導入:25万円
- ・時間単位の有給休暇制度などを新規導入:25万円
など
※取り組み前、36協定の時間外労働時間数等が月80時間を超えていた事業所が対象。
業務改善助成金
業務改善助成金は、設備投資などの業務改善を行い事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げた企業に対する助成金です。主な支給要件は下記の通りです。
- ・事業場内最低賃金を30円以上引き上げる
- ・生産性向上に資する所定の設備投資をおこなう
助成金は生産性向上に資する設備投資などの費用に対して支給され、支給金額は引き上げ金額や対象となる従業員数によって異なります。従業員30人未満の事業場で事業場内最低賃金を30円引き上げた場合、対象者数に応じて支給上限額は次の通りです。
- ・対象者数1人:30万円(60万円)
- ・対象者数2~3人:50万円(90万円)
- ・対象者数4~6人:70万円(100万円)
()内の金額は従業員数30人未満の事業所の上限額です。90円以上引き上げた場合、助成金額の上限は対象者数によって170~600万円になります。
人材確保等支援助成金
人材確保等支援助成金は、内容、業種、対象となる労働者の種類などによって、9つのコースにわかれています。ただし、「雇用管理制度助成コース」と「人事評価改善等助成コース」は2022年4月以降の新規受付は行われていません。
共通する要素として、職場環境改善のための設備導入などの費用を助成するものですが、離職率の低下や給与アップなどの目標達成を支給要件または加算要件とする「目標達成助成」が多いことが特徴です。ただし、制度導入だけで助成が受けられる「制度導入助成」のあるコースもあります。
また、2023年度分より当助成金を含め雇用関係助成金の「生産性要件」が廃止されました。
「テレワークコース」の概要
9コースある人材確保等支援助成金の例として「テレワークコース」について解説します。このコースは、テレワーク勤務に関する制度を新たに整備し、テレワークを可能とする取り組みをする事業主に助成されます。
「テレワークコース」の支給要件と支給額
- テレワーク実施計画を作成し労働局の認定を受けること
- テレワークに関する制度を規定した就業規則または労働協約を新たに整備すること
- 計画に基づきテレワーク制度を導入・実施し、所定の基準を達成すること(対象労働者が週平均1回以上テレワークを実施、など)
支給額の例
上記要件を満たした事業主に対し、「機器等導入助成」として支給対象経費の30%(上限100万円等)が支給されます。また、離職率目標等を達成した場合、「目標達成助成」として支給対象経費の20%または35%(上限100万円等)が加算されます。
両立支援等助成金
職業生活と家庭生活の両立支援や女性の活躍推進に取り組む事業主に対する助成です。主なコースと概要は下記の通りです。ただし、2023年4月現在、「事業所内保育施設コース」の新規受付は行われていません。
両立支援等助成金
出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
男性労働者が育児休業などを取得しやすい職場風土作り
介護離職防止支援コース
介護休業の取得促進、介護のための柔軟な就労制度の導入
育児休業等支援コース
「育休復帰支援プラン」を作成し育休取得と職場復帰を促進
事業所内保育施設コース
事業所内保育施設の設置・運営・増築
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース
新型コロナウイルスにより休業が必要な妊娠中の女性労働者の有給休暇制度の整備
不妊治療両立支援コース
不妊治療のための休暇制度等を利用しやすい環境の整備
各コースの支給要件は、コースごとに定められた制度の整備などの取り組みをおこなうこと、かつ制度利用(休暇取得や制度利用など)実績が出た場合に、所定の助成金が支給されます。
助成金額は、たとえば「出生時両立支援コース」の場合で、1人目の育休取得について、20万円(代替要員を確保した場合、20万円を加算)などとなっています。
人材育成・キャリア開発に関する支援策
現在働いている従業員の教育・育成やキャリア開発に関する支援策も各種あります。ここではその主なものとして、次の4つの助成金を紹介します。
- ・人材開発支援助成金
- ・キャリアアップ助成金
- ・産業雇用安定助成金
- ・企業内人材育成推進助成金
人材開発支援助成金
人材開発支援助成金は、労働者のキャリア形成を目的とした職務関連の職業訓練等をおこなう事業主に対する助成金です。2023年4月に「特定訓練コース」などが統合して「人材育成支援コース」となりました。
人材開発支援助成金
人材育成支援コース
職務に関連した知識・技能を習得させるための訓練を計画に沿って実施する
教育訓練休暇付与コース
一般正社員が対象。有給教育訓練休暇制度を導入し、労働者が当該休暇を取得する。数日間の教育訓練休暇制度と、より長期の長期教育訓練休暇制度がある。
建設労働者認定訓練コース
建設業の中小事業主等が認定訓練を実施する、または建設業の中小事業主が建設労働者に有給で受講させる。
建設労働者技能実習コース
建設業の事業主等が建設労働者に有給で技能実習を受講させる
障害者職業能力開発コース
障害者に対して職業能力開発訓練事業を実施する
人への投資促進コース
雇用後3ヶ月以内の一般正社員等が対象。高度デジタル人材の育成のための訓練等を受講させる
事業展開等リスキリング支援コース
新規の事業展開に伴い、従業員に対して新分野で必要な知識・技能を習得させるための訓練等を受講させる
「人への投資促進コース」の支給要件と支給額
ここでは、「人への投資促進コース」について紹介します。このコースは、従業員に対して次の訓練などを行った場合、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部が助成されます。
- ・高度デジタル人材訓練や成長分野等人材訓練
- ・情報技術分野認定実習併用職業訓練(IT分野未経験者に対する訓練)
- ・定額制訓練(サブスクリプション型の研修サービスによる訓練)
- ・自発的職業能力開発訓練(労働者が自発的に受講した訓練費用の負担)
- ・長期教育訓練休暇等制度(訓練受講のための休暇制度や短時間勤務等制度の導入)
助成率や上限金額は訓練の種類や企業規模などによって異なり、中小企業の助成率は次の通りです。()内の金額が1人1時間当たりの上限額です。
- ・高度デジタル人材訓練など:75%(960円)
- ・情報技術分野認定実習併用職業訓練:60%(760円)
- ・定額制訓練:60%
- ・自発的職業能力開発訓練:45%
- ・長期教育訓練休暇等制度:制度導入経費20万円、休暇1日当たり6000円
また、賃金要件や資格等手当要件に該当すれば助成金が加算されます。
キャリアアップ助成金
有期契約労働者や短時間労働者に対して、正社員化などのキャリア形成を図るための取り組みや処遇改善を実施した事業主に対する助成金で、6つのコースにわかれています。
キャリアアップ助成金
正社員化コース
有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合
障害者正社員化コース
障害者である有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換した場合
賃金規定等改定コース
有期雇用労働者等の賃金規定等を増額改定し、昇給させた場合
賃金規定等共通化コース
有期雇用労働者等と正社員との共通の賃金規定等を新たに規定・適用した場合
賞与・退職金制度導入コース
有期雇用労働者等に賞与や退職金制度、またはその両方を新たに規定・適用した場合
短時間労働者労働時間延長コース
有期契約労働者等の週所定労働時間を5時間以上延長し、社会保険を適用した場合
▼助成額例
「正社員化コース」では有期契約労働者等を正規雇用労働者に転換した場合に57万円、無期契約労働者を正規雇用労働者に転換した場合、28万5000円などが助成されます。
産業雇用安定助成金
産業雇用安定助成金は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け一時的に事業を縮小する事業主が「在籍型出向」を活用して雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主を支援するために2021年に創設されました。
2023年4月に新設されたコースを含め、現在は次の3コースがあります。
産業雇用安定助成金
雇用維持支援コース
「在籍型出向」を活用して雇用を維持する(出向元と出向先の事業主を助成)
スキルアップ支援コース
出向元事業主が、労働者のスキルアップを目的として「在籍型出向」を実施する
事業再構築支援コース
新型コロナウイルス感染症の影響で事業を縮小した事業主が、事業再構築をおこなうために必要な新たな人材を雇用する
「雇用維持支援コース」の支給要件と支給額
ここでは、「雇用維持支援コース」について紹介します。主な支給要件は下記の通りです。
- ・労使協定に基づいて在籍型出向を実施する
- ・出向元事業所は新型コロナウイルス感染症の影響で事業活動が縮小している
- ・出向先事業所に解雇や雇用の減少がない
など
「出向初期経費」として「1人当たり10万円(5万円の加算あり)」が、出向元と出向先に支給されます。また、「出向運営経費(賃金などの経費補助)」として最大「1人1日当たり1万2000円(出向元と出向先の合計)」が最長2年支給されます。
企業内人材育成推進助成金
企業内人材育成推進助成金は、従業員の中長期的なキャリアアップを支援するため「職業能力評価制度」や「キャリア・コンサルティング制度」を導入する事業主などに対する助成金です。
「個別企業助成コース」と「事業主団体助成コース」があり、後者はキャリアアップ支援をおこなう傘下企業の取り組みを支える事業主団体などに対する助成です。ここでは、個別企業助成コースについて紹介します。
「個別企業助成コース」の支給要件と支給額
個別企業助成コースの主な支給要件は、次の人材育成制度を就業規則などに規定して導入し実施することです。
- ・教育訓練・職業能力評価制度:ジョブ・カードを活用しておこなう教育訓練や評価制度
- ・キャリア・コンサルティング制度:ジョブ・カードを活用して実施するコンサルティング
- ・技能検定合格報奨金制度:技能検定に合格した従業員に報奨金を支給する制度
制度導入に対する次の助成金(中小企業)に加えて、訓練などを実施した従業員1人当たり5万円の助成金が支給されます。
- ・教育訓練・職業能力評価制度:50万円
- ・キャリア・コンサルティング制度:30万円
- ・技能検定合格報奨金制度:20万円
上記のほか、従業員をキャリア・コンサルタントとして育成した場合の加算(15万円)もあります。
雇用維持、雇用調整に関する支援策
不況などの理由により、事業活動を縮小して、労働者を休業させたり、離職させたりする際の支援策です。ここでは下記の2施策を紹介します。
- ・雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
- ・労働移動支援助成金
雇用調整助成金
雇用調整助成金は、事業活動縮小によって従業員を休業等させた場合に事業主が支払う休業給付金の一部を助成するものです。労働者の雇用を維持することを目的とした助成金です。新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置の申請は終了しました。
支給要件
- ・休業開始までの3ヶ月間の生産指標が、前年同期と比べて10%以上減少している
- ・休業開始までの3ヶ月間の雇用指標が、前年同期と比べて一定規模以上増加していない
- ・労使協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
支給額
支給額=(平均賃金額×休業手当等の支払率)×助成率
出向を行った場合は出向に要した費用に助成率をかけて計算します。助成率は中小企業が2/3、大企業が1/2です。また、1人1日当たり8355円が上限です。
なお、支給限度日数は原則として1年間で100日分、3年で150日分ですが、出向の場合は最長1年間支給を受けることができます。
労働移動支援助成金
労働移動支援助成金には、経済上の理由で事業活動縮小する事業主が、雇用の維持ができなくてやむなく離職させる労働者に対して再就職支援のための措置を取る場合に、その費用を助成する「再就職支援コース」と、離職を余儀なくされた労働者を早期に雇い入れる場合に助成する「早期雇入れ支援コース」があります。ここでは、「再就職支援コース」の内容を紹介します。
「再就職支援コース」は、以下の場合に助成の対象となります。
再就職支援コースの助成対象
再就職支援
職業紹介事業者に委託して再就職を支援する
休暇付与支援
求職活動のための休暇を付与する
職業訓練実施支援
教育訓練施設等に委託して再就職のための訓練を実施する
助成金額は再就職支援の内容、労働者の年齢などにより細かくわかれています。
65歳超雇用推進助成金
65歳超雇用推進助成金は、高年齢者が意欲と能力のある限り働くことができる生涯現役社会を実現するため高齢者雇用に取り組む事業主に対する助成金で、次の3つのコースがあります。
65歳超雇用推進助成金
65歳超継続雇用促進コース
65歳以上への定年引上げや定年廃止、66歳以上の継続雇用制度などを実施する
高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
高年齢者向けの雇用管理制度の整備等に係る措置を実施する
高年齢者無期雇用転換コース
50歳以上で定年前の有期契約労働者を、無期雇用労働者に転換させる
65歳超継続雇用促進コースの支給額は、実施内容と対象者数(60歳以上の従業員数)などによって異なります。
対象者が10人以上いる場合、定年を65歳に引き上げると30万円、70歳だと105万円の助成金が支給されます。
地方自治体独自制度
人材・労働関係の公的な支援は、厚生労働省がおこなうものが中心ですが、都道府県など地方自治体も独自の助成金、補助金などで企業を支援している場合があります。ここでは京都府と東京都の例を紹介します。
京都府「多様な働き方推進事業費補助金」
京都府の多様な働き方推進事業費補助金は、従業員が仕事と家庭の両立に向けてテレワークを実施したり子育て支援を行ったりする事業主に対する補助金です。取り組み内容によって、次の4つのコースがあります。
- ・テレワークコース
- ・子育てにやさしい職場づくりコース
- ・病児保育コース
- ・育児休業取得促進コース
テレワークコースは、テレワーク制度を新たに導入する中小企業の導入費用(機器やソフトエアの購入費用など)に対し50万円を限度に補助金を支給するものです。補助率は次の通りです。
- ・中小企業など:経費の1/2
- ・小規模企業者:経費の2/3
補助金の申請には、事前に「京都府テレワークセンター」への相談が必要です。
東京都「就職氷河期世代リスタート支援助成金」
就職氷河期世代リスタート支援助成金は、就職氷河期に就職の機会を逃し十分なキャリア形成がなされず正社員としての就職が困難な人を正規雇用労働者として雇用するなどを行った事業主に対する助成金です。
従来の「就職氷河期世代雇用安定化支援助成金」が、2023年度に名称変更されました。主な支給要件は次の通りです。
- 特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)などを受けている
- 対象労働者を正規雇用労働者として採用し1ヶ月継続して雇用している
- 所定の期間、事業主都合による従業員の解雇をしない
など
雇用者数に応じて、次の助成金が支給されます。
- 対象労働者1名:30万円
- 対象労働者2名:60万円
- 対象労働者3名:90万円
また、対象労働者の指導育成に関する業務を専門家(弁護士やキャリアコンサルタントなど)に委託した場合、上記に5万円が加算されます。
人材・雇用関係の助成金、支援策のサポートは社労士に
人材・雇用関係の助成金や支援策は非常に種類が多く、今回の記事で採り上げたのは、そのほんの一部にすぎません。
すべての支援策を調べて、自社に適切なものがどれなのかを判断するのは大変です。迷ったら、人事・労務関係をサポートする専門家である社会保険労務士(社労士)に相談してみましょう。
社労士は、自社にあった支援策の選定から、助成金申請代理まで必要に応じたサポートをしてくれます。
なお、社労士資格を持っていない者が、助成金の代理申請をおこなうことはできません。たとえば、弁護士、税理士、中小企業診断士といった他の士業であっても、助成金の代理申請をおこなうことはできないのです。
中にはまぎらわしい表記で、申請をサポートするといったことをうたっている業者もいますが、そういった業者への依頼はトラブルのもとです。代理申請を依頼したい場合、必ず社労士資格を持っている者に依頼しましょう。
今回紹介した施策の中から、企業の抱えるお悩み別に、それぞれどんな施策がおすすめなのかがわかる、フローチャート資料をご用意しました。こちらから無料でダウンロードし、どの支援策を活用するべきかを検討してみてください!
※本記事の内容は、記事作成日(2023年7月)時点の情報に基づいています。最新の情報は各施策の公式サイトなどをご参照ください。

監修
西岡秀泰(にしおか ひでやす)
西岡社会保険労務士事務所所長。生命保険会社に25年勤務の後、西岡社会保険労務士事務所を開設。社会保険労務士のほか、FP2級資格も保有。得意分野は労働保険、社会保険、金融全般、生命保険。

記事執筆
中小企業応援サイト 編集部 (リコージャパン株式会社運営)
全国の経営者の方々に向けて、経営のお役立ち情報を発信するメディアサイト。ICT導入事例やコラム、お役立ち資料など「明日から実践できる経営に役立つヒント」をお届けします。新着情報はFacebookにてお知らせいたします。

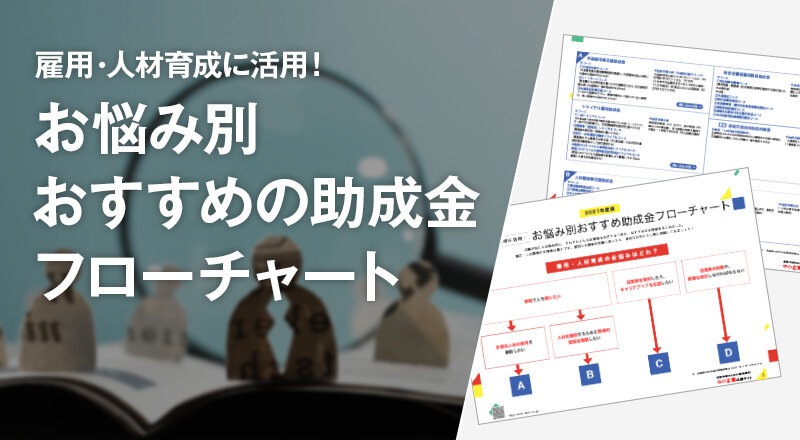
【2023年度版】雇用・人材育成に活用!お悩み別おすすめ助成金フローチャート
代表的な支援策の中から、企業のお悩みに合わせておすすめのものを紹介するフローチャートをご用意しました。ぜひ自社に関係ある支援策を知り、雇用・人材育成活動にお役立てください。